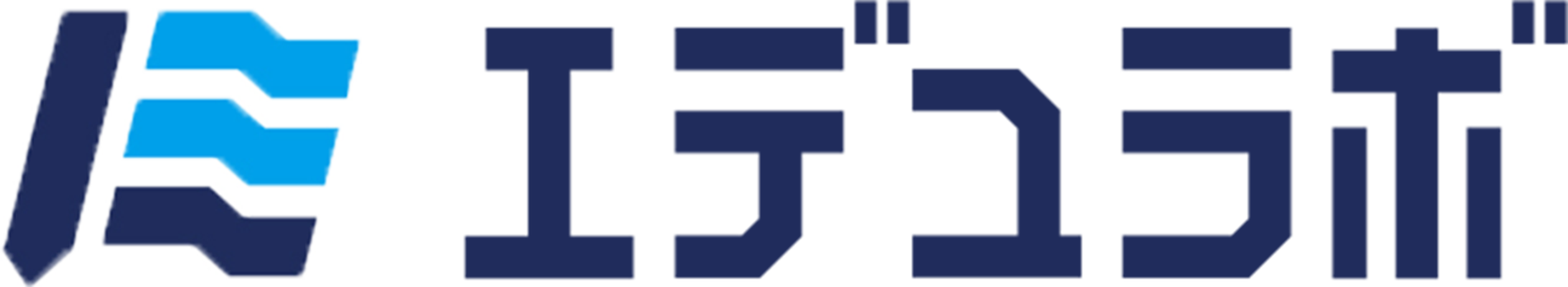本部 運営管理部部長
神道
『人にしかできない仕事』を
増やすために
マクロな視点で
業務効率化を図る

目次
本部スタッフの仕事を教えてください。
A.会社全体を把握する視点、会社全体の戦略や戦術を考える仕事
①会社全体を把握する視点=マクロな視点 をもつ
仕事やプロジェクト全体の目的や目標を理解し、個々の業務に囚われすぎず、全体の流れや進行に影響を与える要因を考慮する必要があります。
また、目先の成果や短期的な結果にとらわれず、長期的な利益や将来的な影響を重視します。たとえば、短期的にはコストがかかるけれども、将来的には大きなリターンが期待できる選択を優先するなどです。
マクロな視点を持つことで、戦略的な判断やリーダーシップを発揮しやすくなり、より大きな成果や影響を与えることができると考えています。
②抽象的なもの(目標や課題など)を具体(タスクなど)に落とし込む仕事
課題を現場の教室長のだけの責任にするのではなく、会社全体でバックアップし解決していく姿勢が大切だと思っています。
例えば、問合せ数や入会数は多いが退会数が多いという教室課題がある場合に、現場の社員に「頑張って改善してください」と伝えるだけでは、人によって対応方法が変わってしまいます。
退会数の多い原因は何か?色々考えられると思いますが、仮説を立て、解決のために会社としてこういう取り組みをしましょうと具体的な戦略・戦術を共有することも仕事の一つです。
③現場に履行してもらえる導線作り
戦略・戦術をただ共有するだけでは物事は進みません。
実際に社員に動いてもらうためには、社員一人ひとりが戦略や戦術の意図を正しく理解している必要があります。
ただ単に「このタスクをやってください」と言うのではなく、何のためにやるのか、遂行することで何が解決されるのかを説明するよう意識しています。
ただし、いざ実行するにあたり、タスクの難易度が高いと履行しきれない人が出てしまいます。
実行するときに迷う人がいないよう、迷いの原因となるものは極力なくなるように工夫しています。例えば、マニュアルや説明動画を準備したり、タスクの工数を最小化するよう工夫しています。
しかし、それでも疑問点・不明点が出てくることもあると思いますので、質問しやすい環境や雰囲気を整えておくように意識しています。
④社員の労働環境を少しでも改善すべく、分単位での業務改善を考える
私は元々システムエンジニアだったので、業務改善・業務効率化をシステムで実現することを行っていました。
システムを導入することで、長時間かかっていた事務作業が数秒で完了するのであれば、浮いた時間は生徒とコミュニケーションをとるなど別のことに有効活用できます。
例えば、まんてん個別では英語の授業で単語テストを実施しています。
授業が始まる前に、講師がテスト用の問題用紙をコピーするのですが、生徒数の多い教室ではコピー機の前に行列ができ、授業が始まっているにも関わらずコピーが完了しないという課題がありました。
こういった待ち時間(無駄な時間)をなくすために導入したアプリがあるのですが、家でどれくらい学習しているかが可視化できるため、紙のテストを行う必要が無くなりました。
コピー作業もなくなったので、今までコピーの為に使用していた時間を生徒とのコミュニケーションに使うことができるようになりました。
⑤人でなくてもできる仕事、人にしかできない仕事を考える
私が現場の教室長に一番してほしい仕事は人にしかできない仕事です。
具体例には、生徒・講師・保護者とのコミュニケーション、モチベーション管理、目標・スケジュール設定や、適切なハードル設定などです。
塾業界の転職者からは、山のような事務作業に忙殺されて、生徒とコミュニケーションをとる時間が無かったとよく聞きます。
教室運営に関する事務作業は確かに多い(データ入力、資料作成など挙げればきりのない)です。
事務作業を完全にゼロにすることは難しいですが、転記作業や二重入力、人の手による集計作業を自動化するだけでも、かなりの工数を削減できます。
入力業務が減ればもちろん人的ミスも減ります。
ミスが減れば修正作業も減りますので、教室長の業務量を圧縮することができす。
人でなくてもできる仕事を極限まで減らし、人にしかできない仕事時間を最大化するのが私の仕事です。
教室長から本部スタッフとなり変化したことはありますか?
A.本部スタッフになってからは答えのない課題が増えました
教室長の時は、答えの分かりやすい課題が多かったです。
例えば、生徒の学力をどう伸ばすか、保護者の期待にどう応えるか、講師をどう育成するか、教室環境をどう改善するかなどです。
過去の経験の中から仮説を見つけ、実行して、効果が無ければ別の方法を試すなど、現場で実行できるので検証もしやすかったです。
しかし、私が今取り組んでいる課題は、明確な答えがないものが多いので、先人の知恵をお借りすることが増えました。
私たちが抱える悩みや課題は、ほとんどの場合において世界初の悩み・課題ではありません。
既に、先人たちが悩み、考え、答えを導き出してくれていますし、大体のことは本にまとめてくれているので、教室長時代よりも本を読む時間がかなり増えました。
そのまま使える答えがピンポイントで見つかることは少ないのですが、他者の意見や経験を知り、先人たちが試行錯誤した結果、うまくいったこと、失敗したことを知ることができるので
仮説を立てるのに非常に役立っています。
PDCAをできる限り早く回すということは教室長の時と変わりませんが、抽象的な課題が増えたので、具体に落とし込むまでの難易度は上がったと感じています。
本部スタッフとして教育サービス業として大切にしていること、自分なりの理念を教えてください。
A.現場の教室長の精神的な余裕を作ること
教室長時代から「生徒に楽しく通ってもらい、しっかり勉強し、点数を上げて、志望校に合格するまで後悔の無いようにやり切る」という理念は変わっていません。
5年間教室長をしていて感じたことは、教育業は利他的な側面が非常に求められるということです。
自分の時間を他者の課題解決のために使うことになるので、自分のこころに余裕が無ければ難しい仕事だと感じていました。
自分に余裕がないと他人に何か与えることは難しいので、まず教室長の精神的な余裕を作ることが大事と思っています。
教室長が生徒と直接会話をし、コミュニケーションをとる時間が増やせるように、効率よく事務作業を進めてもらう必要があります。
事務作業やタスクが多くて忙しい!という状況では、なかなか心のこもった対応はできないと思うので
DX化やICTツール利用での業務量圧縮は、業界トップレベルでやらなければいけないと思っています。
教室長として求める人物像を教えてください。
A.大きく分けるとポイントは5つです
①利他的であること
私たちは、教育サービス業に携わっています。
生徒たちの志望校合格、成績向上を叶えることが私たちの使命であり仕事です。
では、使命遂行のために生徒にただ単に勉強だけさせていればいいのかと言われると、違うと考えています。
生徒のモチベーションを上げる、目標を一緒に見つける、時には人生の先輩として悩み相談にのってあげるなど
自分の時間を他者の為に使う必要があります。
そういったことにやりがいを感じることのできる人を求めています。
②小さな変化に気づけること
例えば、英単語テストでいつも不合格の生徒が合格をしたとします。
いつも不合格だったのは恐らく勉強していなかったからでしょう。
しかし、それが合格したということは勉強を頑張ってきたということです。
そのことに気づいて「すごいやん!英単語しっかり覚えてきたんやね!」と気づいて褒めることができるかどうか。
あるいは、普段よく話しかけてくる生徒が話しかけてこない時は「今日はいつもみたいに元気ないね、どうしたの?」と
気づいて声をかけてあげられるなど、ささいな変化に気づこうとする姿勢が必要です。
③人とコミュニケーションをとることが好きであること
生徒とコミュニケーションをとることはもちろん、より良い教育サービスを提供するために講師の育成を行う必要があります。
人を育成するというのは簡単なことではありません。
未経験講師も多いです。
講師にしてほしいこと、気をつけてほしいことを具体的に言語化して伝えないと、講師は教室長の意図を正確にくみ取って動くことはできません。
また、信頼関係がなければ、こちらの指示には従ってくれません。
信頼関係の構築には適切なコミュニケーションをとることが必要です。
生徒により良い教育サービスを提供するためにも、コミュニケーションをとることが好きな人がこの仕事に向いていると思います。
④自ら進んで変化できること
人は慣れた方法から新しい方法へ変化することを嫌う傾向にあります。
特に仕事においてその傾向は顕著に表れると思っています。
慣れた方法でやれば「この業務は1時間程度で終わるだろう」など、あらかじ目安をつけやすいからです。
しかし、新しいやり方を導入することで1時間かかっていた作業が10分で済むのであればやらない手はありません。
新しいことに臆することなく対応できるかが求められます。
また、業務量圧縮のためにDX化を進めています。
しかし、実験的に進めなければいけないことも多いですし、良かれと思って始めたことが実は弊害ばかりを生んで上手くいかないこともあります。
結局導入中止ということもありますが、こういった場合でも「やってみて、うまくいかないことが分かった」と捉えて次に活かすことが大事です。
より良い教育サービスを提供するために、そして自分たちの働き方を良い方向に改革するためにも、変化を恐れず楽しんでくれる人がまんてん個別には向いていると思います。
⑤素直であること
社員として働くということは責任が生じます。
ルールから逸脱した独自の方法で仕事を進め失敗すると、その人の責任になってしまいます。
自分の価値観や意見はあると思いますが、一度ルールに則ってやってみてください。
もし、その過程で問題点に気づいたり、もっと効率の良い方法があると感じたりした場合は、ぜひ提案してください。
自分だけができればいい、ではなく組織全体として強くなっていけるように考えて動いてもらうことで、ご自身にも大きなリターンがあるはずです。
一緒に成長していきましょう。
最後に入社を考えている方に向けてのメッセージをください
ビジネスパーソンとして生きていく上で、どの業界でも「教育」は避けて通れません。
教育業界でなくても、自分のポジションが上がると、部下ができ「教育」をしていく必要があります。
教育業界では、生徒が100人いれば100人分の「教育」を考える必要があります。
また、講師の育成も考えるともっとたくさんの教育機会があります。
小さなものから大きなものまで課題はたくさん現場に転がっているので、「成績アップ」「志望校合格」を目指しながら、自分も大きく成長できる環境です。
ふとした一言が、こどもの今後の人生に影響を与えることもあるため責任重大ですが
自律的で楽しい人生を、少しでも多くのこどもに送ってもらうために、私たちの「教育」があるのだと思っています。
社会人になっても勉強は続きます。
勉強が好きな方、学んだことを現場で活かしてみたい方、お待ちしております。