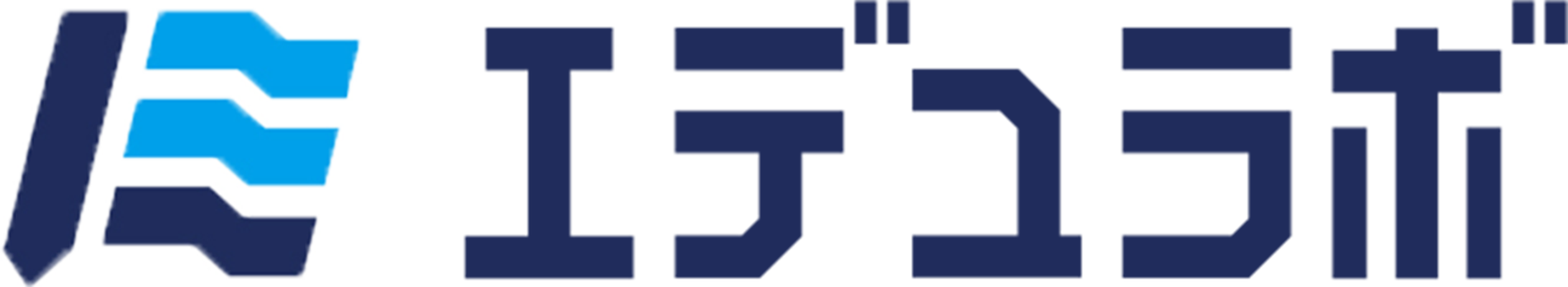東加古川教室 教室長
畠田
きっかけは中学時代の先生。
他者に対して一生懸命
将来を応援できる人になりたい
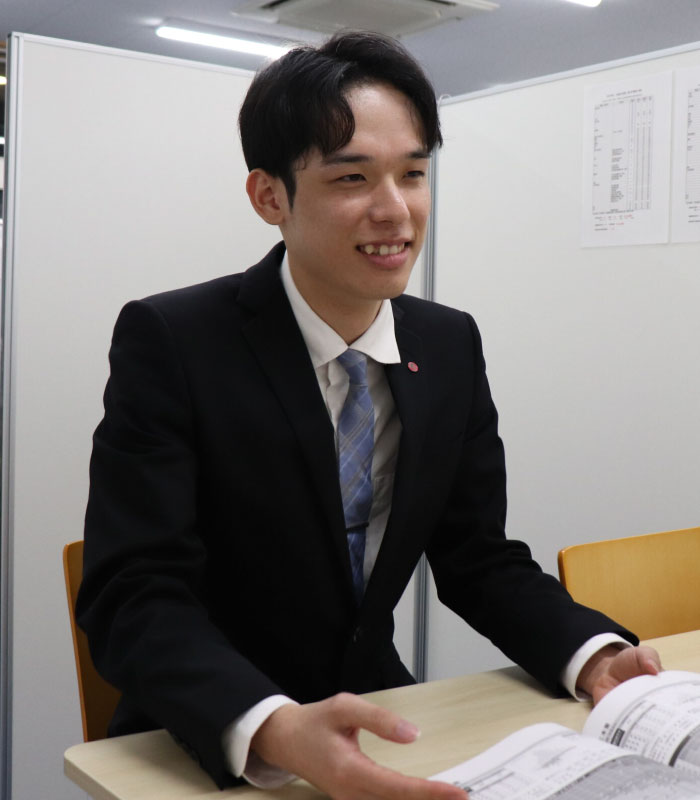
目次
なぜ、塾業界を志望したのか
A.中学生の頃に出会った先生がきっかけです。
新任の先生が僕の担任でした。とても情熱的な先生で、勉強を始めとした進路指導、学校行事など何事にも全力投球の先生でした。特に、進路指導に関しては、まるで自分のことのように親身に相談にのってくださいました。正直言って、僕の進路など先生の人生に大きく影響することはありません。それにも関わらず、僕の将来の夢やなりたい人物像なども含め、複合的に進路のアドバイスをくれた、とても印象に残る先生です。そして僕も、この先生の期待に応えたい、この先生のように他者に対して一生懸命、その人の進路や将来のことを応援できる人になりたいと思いました。
なぜ、学校の先生ではなく塾を選んだのですか?
A.実は、大学生時代のアルバイト先がまんてん個別でした。
この質問に答えるには少し話が長くなるので3つのポイントに分けてお話ししたいと思います。
①塾講師をはじめたきっかけについて
ずばり、この答えは「中学生で出会った先生」がきっかけです。
先生のような他者に対して一生懸命になれる人になりたい、人の役に立てるアルバイトに就きたいと思っていました。僕自身、勉強は一生懸命してきたタイプの人間です。自分のこれまでの勉強・受験の経験を活かして人の役に立てる仕事は何かと考えたとき、塾講師のアルバイトだと思いました。
②塾講師に魅せられ、のめりこむ
塾講師としてアルバイトをスタートしてからは、生徒一人ひとりに合わせた勉強方法、説明を心がけました。褒めて伸びる生徒、悔しさをバネに頑張れる生徒、励ますことで頑張れる生徒など、本当に十人十色の世界です。それぞれの個性に合わせた対応や指導の結果、生徒が新しい単元を学んだ際に理解・納得した時の表情、嬉しそうに点数UPの報告をしてくれること、生徒とのたわいのない雑談、すべてがやりがいでした。
③気づき
ここでの気づきが僕のターニングポイントです。
僕のしてきたことは、個別指導塾だからこそできることだということに気づきました。学校では、一度に30人以上の生徒を指導する必要があります。30人を分け隔てなく指導するには画一的にならざるを得ない場面がどうしても出てくると思います。しかし、個別指導塾であれば、いつでも生徒個人に合わせた指導が可能です。勉強の苦手な生徒には躓いたポイントから復習を、勉強の得意な生徒にはどんどん先取りで予習を進めたり、発展問題に一緒に挑戦したり、個々の学力に応じた手厚いサポートができます。これほどまでに他者に対して一生懸命にその人の進路や将来のことを応援できる仕事は個別指導塾しかないと思いました。
なぜ、たくさんある個別指導塾の中でまんてん個別を選んだのですか?
A.ずばり充実した社内教育制度があると感じたからです。
僕は、大学時代の4年間、ずっとまんてん個別兵庫駅前教室で講師としてアルバイトをしていました。兵庫駅前教室では、新入社員の研修を行っていました。
現場で働く教室長が「教務・生徒対応・保護者対応・事務作業・日々の名もない業務」を実戦形式で研修していきます。塾とは教育サービス業です。サービス業というのは人と接する仕事です。ある程度のことはカテゴライズした上で資料を使って勉強できることもあるかもしれませんが、人と接する仕事だからこそ、生徒や保護者との実際のメールでのやり取り、会話、表情などから要望を聞き出すあるいは読み取る能力が必要になります。この能力は文字で学ぶよりも実践する方がはるかに分かりやすいと思います。現場の人間が実戦形式で指導し、研修生は生でお客様の声に触れることができる。困ったときには必ず先輩がアドバイスをくれる。このやり取りを身近で4年間見てきたので、社内教育制度には120%の信頼があります。
実際に、僕はアルバイト時代に4名の研修生を見てきました。この4名が今も現役で活躍しています。充実した社内教育が社員の現場での活躍に繋がっていると感じます。
当時まんてん個別は実は新卒採用されていませんでしたよね?なぜ、他塾に応募されなかったのですか?
A.この質問には大きく3つのポイントがあります。
①実は、不動産業界にも興味があった
中学生の頃から、教育業界と不動産関係に興味がありました。不動産に関しては趣味の一面も強かったです。不動産の広告を見て、どのような間取り、構造なのか、どのような動線を意識して作られているのか、どのような人がターゲットで作られているのか、自分が住んだらどうなるのか想像するのが好きでした。いずれはまんてん個別で社員として働きたいと思っていたので、どうせなら塾業界ではないところも挑戦してみよう、経験してみようと思い建設関係の会社へ就職しました。
②消えないまんてん個別への思い
講師時代の経験を活かして、塾業界で活躍したいという思いは消えることがありませんでした。
ものすごく記憶に残っている生徒がいます。僕が担当した生徒で、高校受験、大学受験と担当しました。もともとその生徒は勉強が良くできるタイプではありませんでした。そのような生徒に勉強の楽しさを教えるにはどうしたらいいのか、興味関心をもたせるにはどうしたららいいのか、生徒と頻繁に相談したり、教室長とよく意見を出し合ったりしました。そして、教室長は僕の稚拙な意見を否定したり、無視したりすることなくアドバイスをくれて、僕に挑戦する機会を与えてくれました。その生徒は中学、高校の6年間をまんてん個別で勉強を頑張り、第一志望の大学に無事合格し現在通っていた教室で講師としてアルバイトをしています。私としては勉強が嫌いだった元生徒が今では勉強を教える側にたっていること、頑張ってきた勉強方法を現役生に還元していることに自己満足ではありますが達成感を感じております。
この経験を活かして、塾業界で活躍したい、活躍できると確信しました。
そしてたくさんある塾の中でも、まんてん個別に就職したいと思った主な動機は、自分の意見を否定することなく耳を傾けてくれる教室長(※上司)がいたことです。
③三方よしがより良い教育サービスを生む、ライフワークバランスの充実
他塾を考えた際に、同じ塾業界なので業務内容はきっと似たり寄ったりだと思います。仕事のやりがいの次に僕が重要視していたことは、ライフワークバランスです。
まんてん個別はホームページにある通り6時間半勤務です。残業も特にありません。しかし、塾業界では皆さんもご存知の通り、長時間労働、カスタマーセントリックが常態化 しています。しかし、安定した教育サービスを提供するには社員一人一人の心のゆとりも大切です。社員のライフワークバランスも十分に守りつつ、生徒に安定したサービスを提供したいと考えたとき、まんてん個別以外に考えはないと思いました。そして、まんてん個別は6時間半勤務で問題なく円滑に教室の運営ができています。これは、DX化やICTの導入も一役買っていると思います。工夫することで長時間労働から脱却できるのも塾業界です。まんてん個別を筆頭に塾業界に働き方改革を起こす日も近いでしょう。
晴れてまんてん個別に就職されたわけですが、実際に働き始めて感じることを教えてください。
A.やりがいです。
生徒が「テストの点数10点UPした!」「過去最高得点やった!」「授業で自ら挙手して発表頑張ったよ!」など、嬉しそうに報告してくれたり、講師に報告したりしているときの生徒の活き活きと輝く笑顔を見るとやりがいを感じます。
あとやりがいを感じるのは、生徒の選択の幅を広げられたときでしょうか。
具体的に選択の幅を広げるとはどういうことですか?
A.人生は選択の連続だと思っています。
・志望校を選ぶ
・職業を選ぶ
・会社を選ぶ
・見たい映画を選ぶ
・旅行の行き先を選ぶ
人生の中で初めての大きな選択の1つが受験だと思います。そして、特に最初の3つは勉強が大きく影響してきます。職業を選ぶ、会社を選ぶとうのは学歴社会ということもありますが、職業、会社を選んだ後も学問を超えた勉強が一生続くからです。勉強とは学校で習う5教科だけではないと思っています。サービス業であれば、お客様との接し方を学ぶ必要があります。建設業であれば、技術を学ぶ必要があります。これらの勉強というのは学問的な勉強ではありませんが、学生時代に身に着ける基礎学力の高さが、学問領域を超えた分野での勉強に役立つと思っています。例えば、数字が得意なら資料のグラフやデータを正確に読み取ることができます。語学が得意なら英語の資料を正確に読み取ることができます。時事問題に強ければ、社会のニーズに合わせた企画提案ができます。このように、将来の選択の幅を広げるサポートができることにやりがいを感じています。
では、逆にしんどいな、大変だなと感じることはありますか?
A.全てのことに置いて、押しつけにならないように工夫する必要があるというところが大変だと思います。
「 押しつけにならないように」とは、具体的にどのようなことですか?
A. 教室長の使命は、勉強が分かるように導くこと・テストの点数をUPさせることだと思います。しかし、これらを達成する根底には「生徒が楽しく勉強できる」ということが大切だと思っています。極論を言えば、問題演習をひたすら繰り返せば点数は上がると思います。しかし生徒によって現状や目標、得手不得手など異なります。目標を達成するためにどの教科で何をするのか考えて、実行していきます。極論、膨大な演習量を積めばできるようになると思います。しかし、睡眠時間を削ることや学校の授業で寝てしまうなどの弊害が出てきますので、負担になりすぎず要望を叶えられるように、そして生徒が楽しく学習できるよう、良い塩梅を考えるのは大変です。
1年後どのような成長ができていると思いますか?
A.ずばり、教室長としての器や度量が大きくなっていると思います。
面談や保護者対応など様々な行動を振り返った際に「あの時、生徒にこうやって声をかけてあげればよかった」「こういう言い方をしたらより伝わりやすかったかもしれない」のようにこうしておけばよかったかな~と後悔、悩むことも多いです。それは知識、経験不足から来ているので、実際に自身で経験したこと、他の社員から得た経験を実際の現場で落とし込む必要があります。あの時にできなかったことが次には出来るようになる努力の積み重ねが教室長としての器や度量が大きくなることだと考えます。
3年後どのような教室長になっていたいですか?
A.若さを武器に!
3年後でも業界としてはまだまだ若手です。しかし、受験制度や学校の仕組みなどについて「若いから知らない」のではなく、「若いけど知っている」という姿を目指していきます。そして『塾探を探すときに1番に名前が出てくる塾』を目標にしています。特に現在は成績アップにこだわって取り組もうと考えています。
私自身としては『若いけど受験について誰よりも情報を持っている教室長』を目標にしています。その為に今までの行動や受験に対する知識などを人一倍勉強していこうと考えています。そして、目標や決めたことをやり切る1年にしたいです!