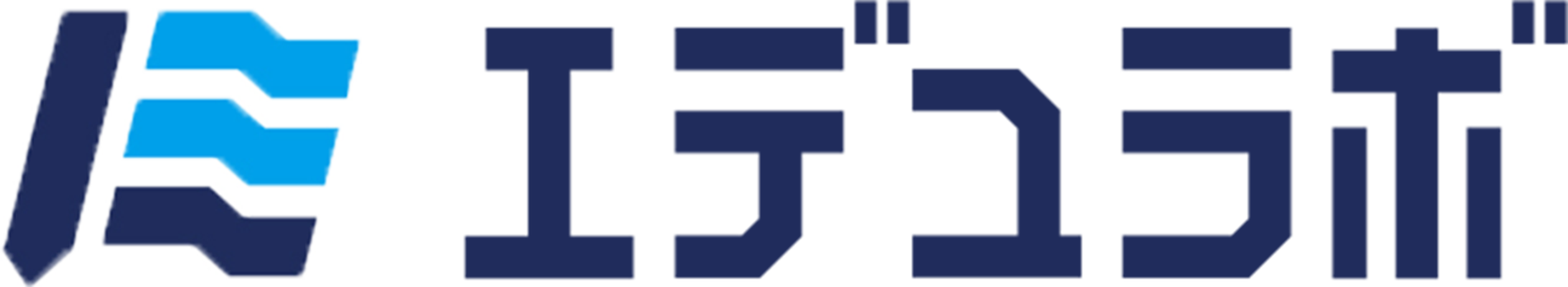湊川教室 教室長
村上
責任感が重要。
他責思考では
人は成長しない

目次
前職について
なぜ、塾業界を選んだのか
①.生徒の笑顔=働きがい
大学時代から、業種や職種を決める上で、就職の軸としてずっと設定し続けてきたものが「働いていて、楽しい仕事かどうか」でした。単純作業の繰り返しや、パソコンに向き合い続ける仕事は、自身の性分に合わないと感じており、適度に相手(顧客)の反応を直接見られることが、働くモチベーションを維持するために必要だと認識していました。また、自分自身が、その分野に今まで関わったことがあり、興味を少しでも持っていることも条件の1つでした。それらに合致していたのが、この教育業界でした。自身が持っている知識・知恵を以て、人を教え育てていく過程で見られる生徒たちの成長。そして、感謝とともにいただく笑顔。良いモノ(お金・名声・権力)よりも、良いコト(ポジティブな体験や経験)を得られる業界だと思い、今も携わり続けています。
②.子どもたちは皆「ダイヤの原石」であることを、自覚させてあげたい
学びに関するサービスの中で、とりわけ塾を選んだ理由は、「学びを通じて、子どもたちに生き生きと過ごしてほしい」と考えたからです。フランスの哲学者ポール・ジャネは「人間の体感時間は、年齢に反比例する」という心理学の法則を発案しました(ジャネーの法則)。言い換えれば、年を取れば取るほど時間の流れが早く感じるというものですが、生まれて間もない2歳までの体感時間をカウントせず、90歳まで生きた場合、人間の体感時間は20歳で半生を終えるようです。それだけ濃密な学生時代を、モノクロではなくカラーで彩ってもらう手助けをするために、塾業界を選びました。すべてのことが得意、逆にすべてのことが不得意な人間は存在しません。得意があれば不得意もある。何かしら向いていることがある以上、子どもたちは皆「ダイヤの原石」であり、どのように磨けば光るのか、どのように輝きたいのか。顕在的なニーズも、潜在的なニーズも含めて、子どもたちに輝き方を伝えてあげることが、今輝けている(=生き生きと過ごせている)私の使命であると感じています。
なぜ、まんてん個別を選んだのか
A.自身の生まれ育った兵庫に、働きながら貢献がしたい
代表が掲げている「兵庫県の教育インフラを目指す」というビジョンに共感し、共にその目標を達成したいと思い、まんてん個別を選びました。すべての子どもたちの教育に携わりたい、という理想は持ちつつも、自身が携われる範囲には限界がある=全世界の子どもたちにすぐ携われない、という現実も認識しています。そこで、携われる子どもたちが限られているなら、自身が生まれ育ち、自身を輝かせてくれた兵庫で生活している子どもたちを、これからも輝かせていきたいと考えています。まんてん個別で子どもたちを導きながら、地元の兵庫に貢献できる。受けた恩を返しながら働けるのは、私にとっての天職です。
教室長になって感じるやりがい
A.携わる人が多くなれば、感謝や笑顔も増える
もともと塾講師のアルバイトをしていたため、自分が教えた生徒から直接感謝や笑顔をいただく機会はありました。教室長として管理・運営業務をすることよりも、最前線で生徒たちを教えることのほうが向いているのではないか。そう考えたこともありましたが、より多くの子どもたちに携わり、そして導いていくためには、自身が直接関わるよりも、自身が育成した講師を用いて間接的に関わるほうが、より多くの子どもたちに携われると考え、教室長を志望しました。講師時代は10人ほどだった教え子(携わっていた生徒)が、今では何十人、百何人と増えたことで、感謝や笑顔の数も数倍になりました。教育業界、様々な職種・働き方がありますが、これだけ多くの感謝や笑顔をいただけるのは、この教室長という仕事ならではだと思います。
教室長になって大変なこと、しんどいことを教えてください。
①子どもの一生に影響を及ぼす、責任の重大さ
濃密な学生時代を塾で過ごす、そこでの過ごし方が今後の人生に多大な影響を与える可能性がある。スポンジのように素直で吸収力の高い子どもたちにとって、眼前に広がっている世界や周りの考えが当たり前だと認識してしまいやすいからこそ、間違った情報や考え方を伝えないように日々注力しています。恥ずかしい話ではありますが、教室長になってから「大人になってからも学習し続ける必要性」を痛感しております。社会人になってからも、空いた時間で勉強し続けることはもちろん大変ですが、生徒たちに「勉強しなさい」と言う前に、まずは自身が勉強していないと示しがつかないので、言葉だけではなく行動でも説得力を出せるよう努めています。
②自身ではなく、講師に指導を任せること
直接自身が教務指導に携わるわけではなく、あくまでも講師が生徒たちの指導を担当するので、自身のスキルやまんてん個別の価値観をどれだけ講師たちに落とし込めるかが重要になります。講師たちもそれぞれの価値観を持っている中で、いかに擦り合わせるか、価値観を共有できるかを考えるのが、大変でもあり楽しさを感じている部分でもあります。こちらの考えや価値観を強要し、全員画一のクローン軍団を作ることも間違いではないと思いますが、生徒の成績アップや志望校合格という大目的を共有し、良い結果を出す過程をある程度講師と相談して委ねてみるのも、ワクワクして楽しく感じられます。
教育サービス業として大切にしていること、自分なりの理念
A.子どもたちにとって良いこと=会社・自身にとっても良いこと
教育業界、とりわけ子どもたちの教育に携わる働き方をしていると、「子どもたちのために労働時間を費やすのは当たり前」「子どもたちのためなのだからサービス残業が当たり前」という考え方が、一昔前にはあったように記憶しています。今では業界の中でも理解が進み、適切な労働時間で働こう、サービス残業は減らそう、という考えが当たり前になりつつありますが、子どもを育てる保護者の中には「聖職者」としての働き方や在り方=無償もしくは安価で良い教育サービスを提供してくれる存在を望む方もいるかと思います。私が教育サービス業に携わる身として意識していることは、顧客(子どもたち・保護者)と我々(会社・自身)がWin-Winの関係でサービスや対価を授受できているか、ということです。顧客が対価以上の過剰サービスを受けるということは、我々が対価に見合っていない過剰労働を強いられていることに他ならず、逆に我々が提供するサービス以上に対価を要求すれば、顧客は不満を覚えてしまいます。どちらかが我慢するのではなく、どちらも良い思いをできるように、サービスの提案や顧客の要望のすり合わせに力を注いでいます。
教室長としての求める人物像
①責任感がある人
この仕事に限らず、どの仕事においても、正社員で働く上で責任感は必要不可欠になってきます。任された業務を、責任を持って実行し、会社が望む結果を出すことこそ、世のサラリーマンが企業に求められていることです。課された目標が達成困難だった際に「できそうにないので無理です」という思考ではなく、与えられた環境でできることは何か、できそうになくてもまず取り組めるかが、教室長として必要だと感じています。他責思考では、人間は成長しません。
②多種多様な経験を積みたい人
将来のキャリア形成のため、様々な経験を積みたい人に、教室長業務はオススメです。営業・事務・販売・管理といった、多様な職種を経験できるので、若いうちから多くの経験値を得られます。苦手だと感じる職種もあるかもしれませんが、すべての職種をそれなりのレベルで実施することを求められ、そのための研修も充実しているので、どの職種も「苦手・不得意だけど出来る」水準以上にこなすことが出来るようになります。
最後に入社を考えている方に向けてのメッセージをください
ワークライフバランスの件もそうですが、高給や休日の多さなど、人によって何が本当の魅力かは変わるので、周りの意見に流されず、5年後・10年後・20年後、それぞれの理想の働き方を想像して、希望する業種・職種を考えてみてください。
「まんてん個別が向かう先」と同じ方向を向いて頑張れる方、ぜひ一緒にまんてん個別を盛り上げていきましょう!