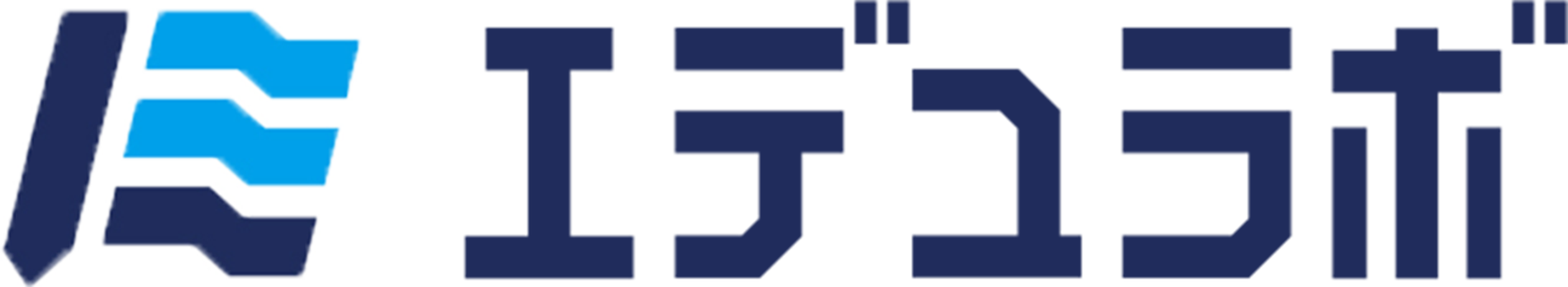東垂水教室 エリアリーダー
川口
生徒の成長が一番のやりがい。
教室長は
生徒のモチベーター

目次
前職について
姫路市にある学習塾に勤めておりました。
なぜ、塾業界を選んだのか
A.人と接することが好きだから、人の成長を手助けする仕事がしたかったからです!
世の中には多種多様な人と関わる、もっと言えばお客様にサービスを提供する仕事があります。しかし、その内容を細かく見ると、例えば携帯ショップ、電気屋さんなどのような販売員さんはお客様の生活がより便利になるような商品を提案します。ホテルマンであればお客様が日常を忘れられるような癒しや休息の時間を提供します。これらは、お客様に便利や快適さを与える仕事です。何かを人に与えるサービス業の中でも塾は勉強を教えるだけでなく人の成長を手助けできる数少ない仕事だと思っています。このように人の成長も手助けできるところが魅力で塾業界を選びました。
なぜ、まんてん個別を選んだのか
A.大きく分けると4つ理由がありますが、一番の理由はやはり働きやすさです!
①働きやすさ、ワークライフバランスの充実
これが一番大きな理由です。僕には子供が2人いて夫婦共働きです。僕が今大切にしていることは、仕事ばかり頑張るお父さんではなく、家事や育児もできる、両立できるお父さんです。まんてん個別は15:30出勤の6時間半勤務なので、土日だけでなく、平日にもしっかりと子供との時間が取れることが魅力で選びました。
②論理的に社内の物事が進む
業務をするにあたり、体育会系のような精神論や勢いだけで強引に物事が進められるということが全くないです。例えば、教室長の数が足りていないのに教室をどんどん展開していき一人で複数の教室を担当するといったことです。僕は、任された教室に通う生徒のプロフェッショナルに教室長はなるべきだと思っています。例えば、表情や声色から生徒の小さな変化に気づけるような人です。生徒の小さな変化に気づくには常日頃生徒とコミュニケーションを取る必要があります。もし、僕が複数の教室を掛け持ちしたとしましょう。そうすると、A教室には月曜日いるけど、B教室には月曜日いない、そうなれば曜日によって僕と会う生徒、会わない生徒が出てきます。それでは、子供たちの小さな変化に気づけないどころか、成長の手助けもできません。まんてん個別には各教室に教室長が必ず配置されています。これによって、生徒一人ひとりとより深く関われるというところも魅力的でした。
③明確な社員の評価基準です
社員への評価基準がしっかりと明記されており、その評価もオープンになっています。経営陣の私情やどんぶり勘定で評価がくだされないので、「何がよくて、何が足りていないか」がはっきりわかり、自分の働き方も考えることができます。
④まんてん個別は本当に授業をしなくてよいというところです
②でもお話ししたところに通じるところでもあるのですが、僕はやはり教室長は自分の教室の生徒のプロフェッショナルになるべきだと思っています。教室長が毎日たくさん授業に入ると、授業を担当する生徒と深く関わることができますが、担当しない生徒との関りが希薄になってしまいます。授業に入ることがなければ、塾に来てくれる生徒全員とあいさつができ、授業時間中に各授業ブースを巡回し声をかけたり、自習に来ている生徒の質問に答えたり、時には生徒の悩み相談にのることもできます。これらは、フリーな時間がないとできないことです。生徒とのコミュニケーションをとるためにも授業に入らずにすむというのはとても良いなと感じました。
教室長になって感じるやりがい
A.ずばり、生徒の成長を感じられたときです!
僕が塾業界を選んだ理由は、人の成長を手助けする仕事がしたかったからです。なので、生徒の勉強に対する意識や姿勢が変わって、勉強する習慣がついたり、成績が上がって生徒が自信をもてたりしたときに、やりがいを感じます。例えば、入塾するまでは学校以外の場所で全く勉強する習慣のなかった生徒が、10分でも20分でも放課後に自ら勉強する時間を設けるようになれば、これは生徒の立派な成長です。「塾での授業後10分間だけでいいから残って単語を一緒に覚えよう」や「テスト一週間前は毎日1時間だけでいいから自習に来てテスト勉強をしよう」など、僕と生徒で約束を作り、生徒が約束を果たしていくことで勉強する習慣がついていく、この習慣を作るための小さなきっかけづくりの手助けができるところにもやりがいを感じています。
教室長になって大変なこと、しんどいことを教えてください。
A.カリキュラムを考えること
就活生の皆さんに包み隠さず、現実を知ってもらうために社員ベクトルでお応えするなら定期テストの直前や季節講習は大変です。まず、定期テスト期間に関しては単純にプレッシャーを感じるからです。教育サービスを受け、勉強するのは生徒ですが出資者は保護者です。保護者の期待にもやはり応える義務があります。また、生徒が一生懸命頑張っているのを目の当たりにしているので、1点でも点数が高く取れるよう、生徒の努力が少しでも大きく報われるようカリキュラムを考えるのが大変だと感じています。
季節講習期は、普段と異なりカリキュラムが大きく変わります。普段は学校の進度に合わせた授業をするのでパターンが決まってきますが、季節講習期は生徒一人ひとりの苦手克服のためのカリキュラムに切り替わるので業務が煩雑になります。1回の授業も無駄にできないので確認作業が増えたり講師への指示がより細かくなるので責任をより感じるとともに大変だと感じます。しかし、季節講習期が終了した時の達成感は最高です。
教育サービス業として大切にしていること、自分なりの理念
A.大きく分けると2つの理念を大切にしています。
①「塾を行かないと行けない場所から行きたい場所に変えること」
サービス業という括りでお話しするならば、ホテルやレジャー施設、テーマパークなどは皆さん行きたくて自ら能動的に行く場所です。しかし、塾は一部の勉強大好きな生徒等を除けば大多数の生徒が受動的に行く場所です。生徒が自ら進んで行きたいと思える教室になるよう、気の合う講師を考えたり、掲示物を作ったり環境を整えるように意識しています。
②言葉を大切にしています。
僕は自分の教室に通う生徒のプロフェッショナルになるべく、日々生徒たちにたくさんの声掛けを行っています。挨拶もそうですが日々の頑張りを言葉で褒める、テスト結果についていい面でも次回に向けた反省面も踏まえて生徒と対話する、進路相談をする、学校での悩みを聞くなど、生徒とたくさん言葉を交わします。僕の発した言葉で、生徒がやる気を出してくれればこれほど嬉しいことはありません。しかし、言葉は時に選択を間違うとやる気をそいでしまったり、しなくてよい心配をさせたりする原因にもなります。多感な年齢の生徒たちだからこそ慎重に言葉を選ぶ必要があります。僕の意見が齟齬なく生徒に伝わり、生徒のやる気のきっかけに少しでもなるように言葉を大切にしています。
教室長としての求める人物像
A. 教育者である必要はないのかなと思います。
教育サービスを真摯に提供する人間である必要はあります。しかし、「私は先生だ!私の言うことを聞きなさい」と偉ぶるのは違うと思っています。例えば、宿題をしてこなかった生徒がいるとします。頭ごなしに「なぜ宿題をしてこないのか?宿題をしてきなさい!」と注意するのではなく、宿題ができなかった原因を生徒と追求し、今後宿題ができるようにどうしたらいいのか相談できる教室長、モチベーターでありたいと思っています。あくまで、生徒と対等な関係で、生徒の意見、言い分にもしっかりと耳を傾けられる人がまんてん個別の教室長に向いていると思います。
最後に入社を考えている方に向けてのメッセージをください
就活生の皆さん、まんてん個別のホームページをここまで読んでいただきたいありがとうございました!
ここまで読んでみていかがだったでしょうか?きっと皆さんは、夢や理想を持って様々な採用ページを閲覧されていると思います。
ここのメッセージまでに読んだ部分で夢や理想もあったと思いますが、「自分にもできるかな?大丈夫かな?」など業務面では不安に感じる部分もあったかもしれません。
確かに、仕事なので大変な部分もあります。しかし、僕を始め誰もが最初は初心者でした。徐々にできるようになりますし、そうなるよう先輩が一生懸命サポートします!
僕自身が証明しています!