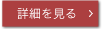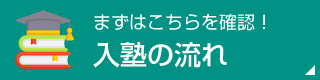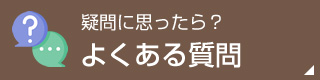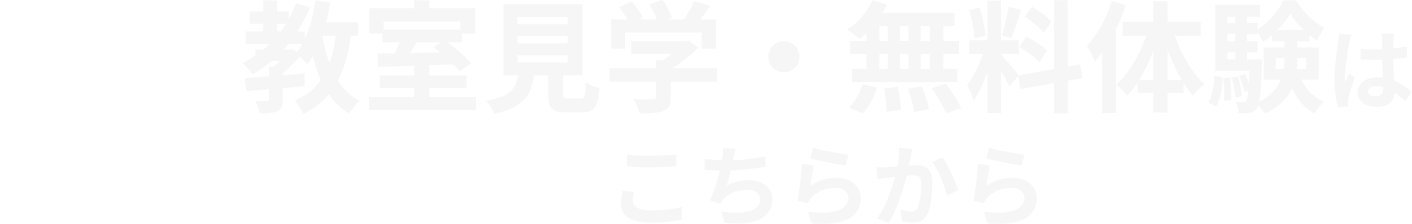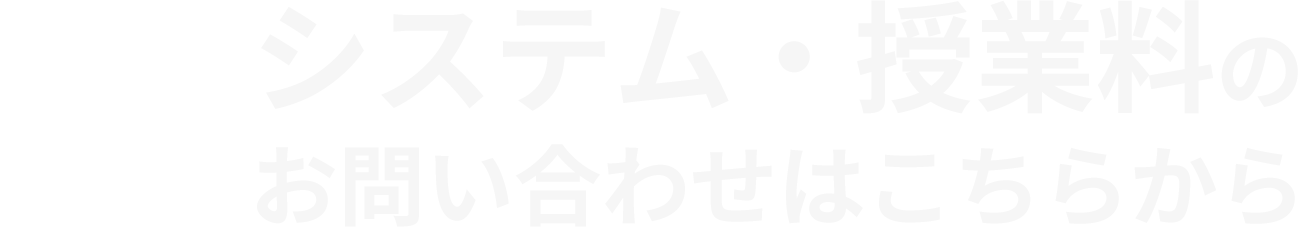ブログ
まんてん通信
数学が苦手な中学生へ|成績が上がる正しい勉強法&定期テスト・入試対策のコツ
2025.04.10
はじめに
「数学が苦手」「どうやって勉強したらいいかわからない」と感じている中学生、そして保護者の皆さんへ。中学数学は、高校受験に直結する非常に重要な教科のひとつです。しかし、つまづいてしまったまま放置してしまうと、どんどん苦手意識が深まってしまうのも事実です。
本記事では、2024年の最新学習事情やyahoo!知恵袋などのリアルな悩みの声を踏まえながら、数学の苦手を克服し、成績を上げるための「正しい勉強法」について詳しく解説していきます。
勉強のコツはもちろん、東大生が実践していた方法や、定期テスト・高校受験に向けた対策法もご紹介。読んだその日からすぐに始められるステップも提示するので、ぜひ最後まで読んで、数学を「得意」に変える第一歩を踏み出しましょう。
数学が苦手になる原因とは?
中学生の多くが「数学が苦手」と感じてしまうのには、いくつかの共通した原因があります。まず第一に挙げられるのが、「前の単元の理解が不十分なまま、次の内容に進められてしまうこと」です。数学は積み上げ型の教科であり、例えば一次方程式がわからないと関数に進んだときに理解が追いつかず、結果として「全部わからない」と感じてしまいます。
このようなつまづきは、定期テストや授業の中で何度も繰り返され、苦手意識がどんどん強くなってしまうのです。実際、yahoo!知恵袋でも「なぜ数学だけこんなにできないのか」「どの問題もつまってしまう」といった悩みが頻繁に投稿されています。
また、「わからない」という気持ちを口に出せず、先生や保護者にも言えずに我慢してしまう生徒も少なくありません。こうした状況が続くと、数学に対する嫌悪感すら芽生え、「自分には無理」とあきらめてしまうようになります。
さらに、中学に入ると授業のスピードが速くなり、全体の理解を待ってくれる場面が減ってきます。教師側が「できて当然」として授業を進めることもあり、なかなかついていけない子どもにとっては苦痛になってしまうのです。
このような苦手の連鎖を断ち切るには、「なぜ自分は苦手なのか」を客観的に分析する必要があります。たとえば、「計算ミスが多い」「文章題になると理解できない」「グラフの意味がわからない」など、自分の状況を正しく把握することが出発点です。
また、親が子どもの苦手意識に対して「ちゃんとやりなさい」とプレッシャーをかけてしまうと、ますます勉強が嫌になってしまいます。まずは「どこでつまづいているのか」を一緒に見つけ、共に向き合うことが大切です。
この記事では、このあと「おすすめの勉強法」や「単元別の対策法」、さらに「高校受験に向けた具体的な方法」まで紹介していきます。正しいステップを踏めば、数学は必ず得意科目に変わります。焦らず、一歩ずつ進めていきましょう。
東大生が実践したおすすめ勉強法とは
数学を得意にするためには、ただ問題を解くだけでは足りません。多くの東大生が中学時代から意識していたのは、「なぜ解けたのか」「なぜ間違えたのか」を言語化し、自分の頭で理解することです。ここでは、東大生たちが実際に行っていたおすすめの勉強法をいくつか紹介します。
まず基本中の基本として、「ミスノート」を作ること。問題を解いて間違えたら、なぜ間違えたのかを単行で簡潔にまとめます。これは単なる解説の写しではなく、自分が「どう勘違いしたのか」「どのポイントを見落としたのか」を明確にする作業です。記録しておくことで、次に同じミスをしまうことを防ぎます。
次におすすめしたいのが、ソフトカバーの薄いワークを使った反復学習。分厚くて難しそうな参考書ではなく、「薄い問題集を何度も解く」ことで、理解が深まります。特に中学生には、定期テストや授業内容に直結したワークの活用が効果的です。1冊を3周することで、内容が体にしみ込むようになります。
また、最近では映像授業を活用する生徒も増えています。難しい単元でも、動画で図解やアニメーション付きで説明されると理解が深まりやすいです。おすすめは、学校の内容に沿ったカテゴリ別の講座がある教材。たとえば、東大家庭教師友の会が提供する授業などは、特にわかりやすいと評判です。
「わからない」を放置せずにすぐ解決するために、教えを受けられる環境も重要です。個別指導塾やオンライン指導を活用すれば、自分の疑問をすぐに質問できます。また、日常の中で「今日やること」を1つ決めて、それを実行できたらポイントをもらえるようなごほうび制度を使うのも、やる気を維持する工夫になります。
もうひとつ大事なのが、勉強したことを「アウトプット」すること。人に説明したり、ノートにまとめたりすることで理解が深まります。これは「解こる力」を養う練習でもあります。
勉強は、ただ長時間やればいいわけではありません。効率よく、そして継続的に行うことがカギです。東大生が実践していた方法を参考に、自分に合ったスタイルを見つけていきましょう。
教科ごとの対策と勉強の進め方
数学は一つの教科ではありますが、単元によって求められる考え方や解き方が大きく異なります。つまり、「一つの勉強法ですべてに対応する」のは難しいということです。ここでは、中学数学の代表的な単元ごとに、効果的な勉強の方を紹介します。
まずは「計算問題」。これはすべての基礎となる単元であり、定期テストや高校受験でも頻出です。計算問題では「スピード」と「正確性」が求められます。特に中1の正負の数や文字式、方程式の段階でつまずいていると、その後の関数や図形に大きく影響します。ポイントは、毎日少しずつでもいいので反復練習すること。今日解いた問題を翌日も再度解いてみるなど、「繰り返すこと」で定着します。
次に「文章題」。ここが苦手な生徒は非常に多いですが、その理由の多くは「日本語としての読解」ができていないことです。文章を読みながら、条件をメモに書き出す、図にして整理するなどの工夫が重要です。「解こうとする前に、問題を分解する」意識を持つと、急にやりやすくなります。
そして「図形問題」。ここでは空間認識力が必要になります。問題文を読むだけでなく、自分で図を描くことが何より大切です。中2・中3で出てくる証明問題では、正しい順序での論理の積み重ねが求められるため、書く練習を積み重ねることが必要です。ここでも、「なぜこの順番で書くのか?」を自分の言葉で説明できるようにしておくと理解が深まります。
また、教科ごとに「得意・苦手」があることを把握しておくことも大切です。例えば関数が苦手なら、グラフや表を使って直感的に理解できるような問題から取り組む。証明問題が苦手なら、「よく使われる論理パターン」を単行カードにまとめておくのもおすすめです。
保護者としてできることは、「どの単元でつまづいているのか」を一緒に確認してあげることです。そして、必要に応じて塾や個別指導塾などのサポートを活用し、「わからないままにしない環境」を整えることが重要です。
苦手な単元を一つずつ潰していくことは、「わからない」から「できた」への変化を体験できる貴重なチャンスです。これが生徒にとっての喜びにつながり、学ぶことへの意欲を高めてくれます。
高校受験に向けた具体的な対策法
中学生にとって、高校受験は大きな目標のひとつです。特に数学は受験の中でも得点差がつきやすく、対策次第で合否が分かれる教科でもあります。ここでは、2024年の最新傾向を踏まえた、志望校合格に向けた具体的な対策ステップを紹介します。
まず最初にやるべきことは、自分の現状を正確に把握することです。どの単元が苦手か、テストの点数はどの程度か、志望校の出題傾向と自分の実力とのギャップを見極めましょう。この「現状分析」ができれば、次に何をするべきかが明確になります。
続いて、「志望校の出題傾向を知る」ことが重要です。ランキング上位の難関校では、関数・証明・空間図形などの思考力を問う問題が出題されやすい一方、中堅校では計算力や文章題などの基礎力重視の問題が多くなります。学校ごとの傾向は教育委員会の過去問題集や、塾が提供している情報サイトなどで確認できます。
そのうえで、「いつ何を勉強するか」を逆算して計画することが大切です。どの教材を、どの順番で、どのくらいの量やるのかを決めておくことで、勉強に迷いがなくなります。ここで活用したいのが、「単元ごとの勉強計画表」。市販の受験対策ノートや商品(参考書)に付属しているものを使ってもよいでしょう。
また、模試を受けて「本番形式」に慣れることも大事です。定期的に模試を受けていれば、自分の弱点を定期的に見直すことができ、どのような問題に対してどう進めるべきかが明確になります。模試の成績だけを見るのではなく、「どの問題をなぜ間違えたのか」を振り返ることが最大の学習材料になります。
中学3年生になると、部活や学校行事との両立もあり、計画通りに進めるのが難しくなることもあります。そんなときは、保護者の声かけや、個別指導塾・オンライン指導などのサポートを活用するのもおすすめです。最近では、東大家庭教師友の会のように、東大生が志望校別に対策を教えてくれるサービスも人気です。
受験勉強を「きついもの」と感じてしまうと、モチベーションの維持が難しくなります。そこで、「合格したらどんないいことがあるのか」をリストアップするのも効果的です。制服がかわいい、部活が強い、通学が便利など、小さなことでもOK。それがやる気を支える支柱になります。
定期テスト対策のコツとスケジュール
定期テストは、中学生にとって「勉強したことが実際に身についているか」を確認できる大切なチャンスです。そして、その結果は内申点に直結し、高校受験にも影響を与えます。だからこそ、数学の定期テストでは確実に点を取るための対策とスケジュール管理が必要です。
まず、定期テスト対策は「テスト範囲が配られてから始める」では遅すぎます。日頃から授業で扱った内容をその日のうちに軽く復習し、ワークや問題集を進めておくことが最大のポイントです。特に苦手な単元は、「1日1問でもいいから継続する」ことが大切です。
おすすめは、3週間前からのテスト準備。以下のようなステップで進めると効果的です:
-
3週間前:出題範囲の確認とスケジュール作成。教科ごとに時間配分を考える。
-
2週間前:ワークを1周して、全体の理解度をチェック。間違えた問題はノートに単行でまとめておく。
-
1週間前:2周目のワークと予想問題に挑戦。特にミスが多い箇所を重点的に。
-
前日〜当日:暗記ポイントや計算ミスしやすい問題を再確認。焦らず「今できること」に集中。
重要なのは、「間違いを分析し、次に活かす姿勢」です。ミスした原因を考えずにしまうと、また同じ間違いを繰り返してしまいます。「どのステップでつまずいたか」「なぜその式にならなかったのか」を言語化してノートにまとめると、自分の苦手な「型」が見えてきます。
また、モチベーションを保つためにポイント制を取り入れるのもおすすめです。たとえば、「30分勉強できたら1ポイント」「ワーク1ページ終わったら2ポイント」などルールを決め、一定ポイントがたまったらご褒美がもらえる仕組みにします。これは中学生だけでなく、小学生や大人にも有効な方法です。
保護者の役割も非常に重要です。勉強を「やりなさい」と言うのではなく、「がんばってるね」「今日は何を勉強したの?」など、フォローの声かけで子どものやる気を支えましょう。さらに、テスト後のフィードバックとして、「何ができたか」「どこが成長したか」を一緒に話すと、次のテストへの意欲につながります。
教材選びにも工夫が必要です。カテゴリごとに分かれた問題集や、急上昇ワードで人気の映像教材、ソフトカバーで使いやすい参考書など、自分に合ったものを選びましょう。中には、ランキング形式で紹介されている教材記事もあり、比較検討に便利です。
定期テストは、ただの通過点ではなく「勉強の成果を実感するタイミング」です。ここで得意分野を作り、自信をつけることが、高校受験にもつながっていくのです。