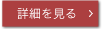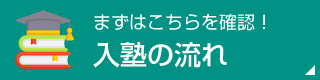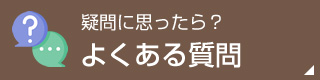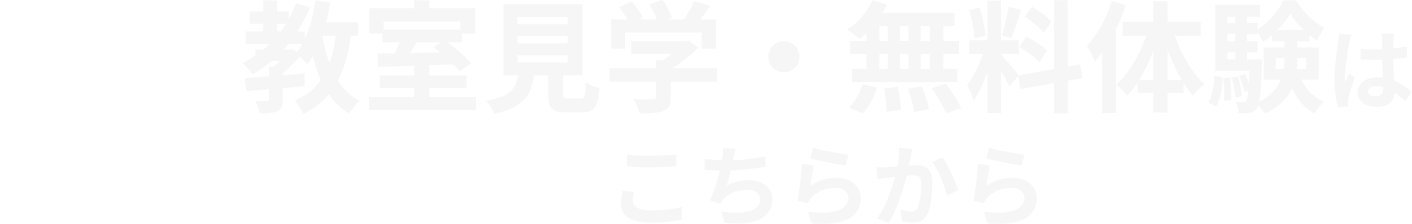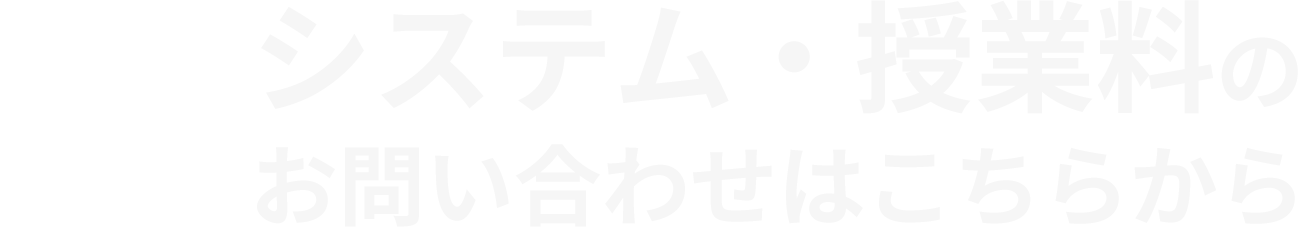ブログ
まんてん通信
効率アップ!誰でも実践できる速読トレーニングのコツと方法
2025.05.11
効率アップ!誰でも実践できる速読トレーニングのコツと方法
目次
速読
試験勉強や課題でたくさんの本や資料を読まなければならない学生生活。「もっと速く読めたら…」と感じることはありませんか?本記事では、学生の勉強効率を大幅に上げる速読トレーニングのコツを紹介します。科学的に効果が実証された方法ばかりなので、誰でも簡単に実践できます。数週間の継続で、あなたの読書スピードは2〜3倍に向上するでしょう。試験対策や課題にも活用できる速読のスキルを、ぜひこの記事で身につけてください。目次を参考に、気になるセクションからチェックしてみましょう。今すぐ速読の世界へ踏み出す第一歩として、この記事をご活用ください。
目次
- 速読とは?効果と重要性について
- 速読の科学的メカニズムとその効果
- 初心者でも実践できる速読トレーニング4つの基本ステップ
- 速読の具体的方法:5つの即効性テクニック
- 英語文献に特化した速読のコツとポイント
- 速読習得でよくある障害と克服法
- 速読トレーニングアプリ・ツールのまとめ
- よくある質問(FAQ)
- 速読マスターへの道:まとめと次のステップ
速読とは?効果と重要性について
速読とは単に教科書や文章を速く読むだけでなく、内容の理解度を保ちながら読書スピードを上げる技術のことです。大学や高校での勉強では毎日膨大な量の読み物が課され、それらを効率よく処理する必要があります。速読は単なる読書テクニックを超え、学習効率を高める重要なスキルなのです。
速読の最大のメリットは、短時間で多くの情報を取り入れられることです。通常、学生は1分間に200〜300文字程度しか読めませんが、速読トレーニングを受けた者は1000文字以上読むことも可能になります。試験勉強や課題をこなす時間が大幅に短縮できるでしょう。
また速読は記憶力の向上にも効果があります。速く読むためには集中力が必要で、この集中状態が脳の活性化を促し、記憶の定着にも役立ちます。文章全体をイメージとして捉える訓練は、テスト勉強における理解力と記憶力の両方を鍛えることになるのです。
レポート作成時の資料読解、試験前の短時間での教科書読み直し、英語の多読課題など、学生生活のあらゆる場面で速読は役立ちます。誰にとっても、より多くの知識を得るための有効な学習方法なのです。
速読は単に速く読むテクニックではなく、脳の使い方を最適化する方法だと考えましょう。目的に合った読み方ができるようになれば、必要な情報を必要なだけ取り入れる自由が手に入り、テスト勉強の効率が格段に上がります。次のセクションでは、なぜ速読が可能なのか、その科学的メカニズムについて解説します。
速読の科学的メカニズムとその効果
眼球運動と速読の関係
私たちが教科書や参考書を読むとき、目は一定のリズムで動いています。通常の読み方では、1つの単語ごとに目を止めてしまうため、ページ全体を読むのに多くの時間がかかります。速読のトレーニングでは、この眼球運動を改善し、一度に捉える単語の数を増やすことを目指します。
実際、熟練した速読者の目は、1回の停留で複数の単語や文を同時に捉えられるようになります。これにより、ページあたりの眼球停留回数が減少し、読書スピードが大きく向上するのです。授業ノートや教科書を何度もトレーニングで読むと、この感覚が自然と身につき、文章を面として捉える能力が発達します。
脳の情報処理メカニズムと速読
脳は膨大な情報処理能力を持っていますが、学生を含む多くの人はその一部しか活用していません。通常の読書では、頭の中で音読するように読む「サブボーカリゼーション」という現象が起こりますが、これが読書速度を制限する大きな要因となっています。
速読トレーニングでは、このサブボーカリゼーションを抑制し、文字から直接意味やイメージを捉える方法を学びます。これにより脳の処理速度が上がり、情報の取り込み速度も向上します。言葉を一つずつ処理するのではなく、文章のかたまりとして処理することで、理解の質を保ちながら速度を上げることが可能になるのです。
集中力と理解度の関連性
速読と理解度は対立するものではありません。むしろ、適切な速読トレーニングは集中力を高め、結果として理解度も向上させます。授業中や自習時にありがちな「読みながら他のことを考えてしまう」状態を防ぎ、文章に没入する状態を作り出します。
科学的研究によれば、適切なスピードで読むことで脳が活性化し、集中力が維持されやすくなります。この状態では情報の処理と記憶の定着が効率的に行われ、読んだ内容の理解度と記憶の保持率が向上するのです。試験前の短時間で多くの内容を復習する必要がある学生にとって、速読は単に速く読むための技術ではなく、脳の潜在能力を引き出す学習法だと言えるでしょう。
初心者でも実践できる速読トレーニング4つの基本ステップ
ステップ1:眼球運動の強化トレーニング
速読の基礎となるのは眼球運動の改善です。多くの学生は教科書を読む際、一つの単語ごとに目を止めてしまいますが、これでは読書スピードに限界があります。眼球運動を強化するには、ページの中央から左右に視線を動かす練習が効果的です。
具体的なトレーニング方法としては、教科書のページの中央に指を置き、その指を上から下へと一定のリズムで動かしながら、視線はその指を追うようにします。このとき、目だけを動かし、頭は動かさないよう意識しましょう。最初は理解できないかもしれませんが、繰り返すうちに周辺視野が広がり、一度に捉えられる文字量が増えていきます。
このトレーニングは授業の合間や通学時間に1日5分から始め、徐々に時間を延ばしていくといいでしょう。継続することで、目の動きが滑らかになり、ページ全体を効率よく読める状態に近づいていきます。
ステップ2:周辺視野の拡大エクササイズ
速読の重要なポイントは、周辺視野を活用して一度に多くの情報を取り入れることです。通常、学生は中心視野だけを使って読んでいますが、周辺視野も活用することで読書速度を大きく上げることができます。
トレーニングとしては、三角形や逆ピラミッド型に配置された単語群を一瞬で認識する練習が有効です。例えば、ノートに上部から下部に向かって徐々に幅広くなる形で単語を配置し、それを一度の視線移動で読み取る練習をします。
最初は3〜5単語から始め、徐々に一度に読み取る量を増やしていきましょう。このトレーニングを続けると、教科書の一行全体を一度に捉えられるようになり、読書スピードが自然と向上します。
ステップ3:不要な音読化(サブボーカライゼーション)の抑制
多くの学生は読書中、頭の中で声に出して読むように文章を処理しています。これを「サブボーカライゼーション」と呼び、読書速度を制限する大きな要因となります。音読のスピードは通常1分間に150〜200単語程度ですが、視覚的な処理能力はその何倍もあります。
サブボーカライゼーションを抑制するトレーニングとしては、意識的に読書スピードを上げて頭の中で声に出して読む余裕をなくす方法や、読みながら単純な曲をハミングするなどの方法があります。また、意識的に「単語の意味」をイメージとして捉える練習も効果的です。
このトレーニングは最初は違和感がありますが、継続することで文字から直接意味を取り込む感覚が身につき、読書速度が飛躍的に向上します。理解度を維持するために、最初は教科書の簡単な章から練習し、徐々に難しい内容に挑戦していくことをおすすめします。
ステップ4:集中力と持続力の向上メソッド
速読には高い集中力が不可欠です。どんなに目の動きが速くなっても、集中力が途切れてしまっては効果半減です。集中力を鍛えるトレーニングとして、時間を区切った集中読書が効果的です。
例えば、スマホのタイマーを10分にセットし、その間は完全に教科書読解に集中する練習をします。このとき、読んだページ数をメモしておき、次回はそれを上回ることを目標にします。短時間で集中して読む習慣がつくと、自然と読書速度も上がっていきます。
また、勉強環境も重要です。図書館のような静かで適切な明るさの場所を選び、スマートフォンなど注意を散らすものは遠ざけましょう。集中力のトレーニングは、速読だけでなく他の学習や試験勉強にも良い効果をもたらします。
速読の具体的方法:5つの即効性テクニック
フィンガーリーディング(指で誘導する読書法)
フィンガーリーディングは、指やペンなどを使って視線の動きを誘導する方法です。多くの速読者が活用するこの技術は、目の動きを安定させ、集中力を高める効果があります。視線が単語から単語へとランダムに飛ぶのを防ぎ、一定の速度で前進することを助けます。
具体的なやり方は、人差し指やペンの先を教科書の行の下に置き、一定の速度で右から左へと滑らかに動かすだけです。最初は普通の読書スピードで、慣れてきたら徐々に指の動きを速めていきます。指より速く読もうとすると混乱するため、指の動きに目を合わせることが重要です。
この方法のメリットは簡単に始められることと、即効性があることです。初心者でもすぐに読書スピードの向上を実感できるため、試験前の短時間での教科書読破にもおすすめです。
チャンキング(情報のかたまり読み)
チャンキングとは、文章を単語単位ではなく、意味のあるかたまり(チャンク)として捉える読み方です。私たちの脳は、関連性のある情報をグループ化して処理する能力を持っています。この特性を活用することで、読書スピードを大きく向上させることができます。
例えば「教育心理学の基本理論」という文を読むとき、5つの単語を別々に処理するのではなく、一つのイメージとして捉えます。トレーニングとしては、教科書内の関連する単語群を意識的にグループ化して読む練習を繰り返します。
慣れてくると、文章構造を瞬時に把握し、重要な情報を効率よく抽出できるようになります。チャンキングは理解度を維持しながら速度を上げられる方法として、試験勉強や課題文献の読解に特に効果的です。
スキミングとスキャニングの使い分け
速読の重要なスキルとして、「スキミング」と「スキャニング」の適切な使い分けがあります。スキミングは教科書や参考書の概要を把握するために全体を素早く読む方法で、スキャニングは特定の情報や単語を探すために文章をざっと見る方法です。
スキミングでは、最初と最後の段落、各段落の最初の文、見出しや太字などを中心に読むことで、短時間で文章の要点を把握します。スキャニングでは、探している情報に関連するキーワードに注目し、それを見つけたら周辺を詳しく読みます。
読書の目的に応じてこれらの技術を使い分けることで、必要な情報だけを効率よく得ることができます。例えば、試験範囲の予習にはスキミングが、過去問から出題傾向を探る場合にはスキャニングが適しています。
速度調整型読書トレーニング
速読を習得するうえで効果的なのが、意識的に読書速度を変化させる「速度調整型トレーニング」です。このトレーニングでは、通常より速いスピードで読む「速読フェーズ」と、理解度を確認する「確認フェーズ」を交互に行います。
具体的には、まず自分の通常の読書速度を知り、その2倍の速さで3〜5分間読む練習をします。このとき完全な理解は求めず、とにかく速く目を動かすことを意識します。次に、読んだ内容について思い出せることをノートにまとめ、理解度をチェックします。
このトレーニングを繰り返すことで、脳が高速処理に慣れていき、次第に理解度を維持したまま速度が向上していきます。速度を意識的に上げることで、自然な読書でも以前より速く読めるようになり、試験勉強の効率が格段に上がるでしょう。
メタ認知を活用した理解度強化法
速読で重要なのは、速度だけでなく理解度の維持です。「メタ認知」とは自分の思考プロセスを客観的に認識する能力のことで、これを活用することで理解度を高めながら速読することができます。
具体的な方法としては、読む前に「この教科書から何を得たいか」という目的を明確にし、読みながら「今何について書かれているか」「これまでの内容とどう関連しているか」を常に意識します。また、読み終わった後は内容を友達に説明するつもりで要点をまとめてみましょう。
この方法により、ただ文字を追うだけでなく、情報を構造化して取り込むことができ、速読と理解の両立が可能になります。試験勉強や専門書の理解など、複雑な内容を扱う場合に特に効果的なテクニックです。
英語文献に特化した速読のコツとポイント
英語と日本語の文章構造の違いと対処法
英語と日本語では文章構造に大きな違いがあり、これが英語文献の速読を難しくしています。日本語は主語が省略されることも多く語順も比較的自由ですが、英語は「主語+動詞+目的語」の順が基本です。この構造の違いを理解し、英語の文の流れに慣れることが重要です。
英語速読のコツは、文の主語と動詞をすぐに見つけ、文の骨格をつかむことです。長い文では、カンマやセミコロンで区切られた単位ごとに意味をとらえていきます。また、英語は接続詞や前置詞が文の関係性を示す重要な役割を果たすため、これらの単語に注目することで文章の流れを把握しやすくなります。
トレーニングとしては、簡単な英語ニュース記事から始め、徐々に英語の教科書や論文に移行するのがおすすめです。オンラインの英語ニュースサイトは無料で多くの記事を読めるため、日々の練習に最適です。
英語速読における重要な読解パターン
英語の文章には特有のパターンがあり、これを理解することで速読の効率が上がります。例えば、英語の教科書や論文では最初と最後の段落に重要な情報が集約されていることが多く、各段落の最初の文がその段落の要点を示していることが一般的です。
英語の文章を速読する際は、これらのパターンを活用し、戦略的に情報を拾っていきます。見出しや太字、箇条書きなどの視覚的な手がかりも積極的に活用しましょう。また、図表やグラフが含まれる場合は、これらを先に見ることで内容の全体像を把握しやすくなります。
速読と精読を使い分けることも重要です。まず全体を速く読んで概要をつかみ、必要な部分だけを詳しく読み直す「多層的読解」が効率的です。試験勉強や課題提出の締め切りが迫っている場合は特に、この方法で効率よく必要な情報を得ることができます。
英語速読のための語彙強化戦略
英語の速読を妨げる大きな要因の一つが、単語の意味がすぐに分からないことです。効率的な速読のためには、基本的な語彙力を強化することが不可欠です。特に高頻度で使用される単語や、自分の専攻分野の用語をしっかり覚えておくことが重要です。
語彙強化の効果的な方法としては、フラッシュカードアプリを使った学習や、読んだ文章の中から知らない単語をピックアップして単語帳を作る方法などがあります。また、同じ単語でもコンテキストによって意味が変わることがあるため、文脈の中で単語を覚えるようにしましょう。
同時に、知らない単語があっても文脈から意味を推測する力も重要です。すべての単語の意味が分からなくても、文全体の意味が把握できれば速読は可能です。この推測力を鍛えるには、辞書を使わずに英語の記事を読む練習が効果的です。
速読習得でよくある障害と克服法
理解度低下の不安とその対処法
速読を始めると多くの学生が「速く読むと内容が理解できなくなるのでは」という不安を感じます。確かに、ただ目だけを速く動かしても、理解度は低下してしまいます。しかし、適切な速読トレーニングでは理解度を維持しながら速度を上げることが可能です。
対処法としては、まず理解度チェックを習慣にすることが大切です。読み終わった後、内容を簡単に要約してみる、重要なポイントを箇条書きにしてみるなどの確認作業を行いましょう。理解度が低いと感じたら、速度を少し落として再度チャレンジします。
また、速読は一度に習得できるものではありません。高校や大学の教科書の簡単な章から始め、慣れてきたら徐々に難しい内容に挑戦していきましょう。さらに、テスト勉強の目的を明確にしておくことで、何を読み取るべきかが分かり、効率的な読書が可能になります。
集中力の維持が難しい場合の解決策
速読には高い集中力が必要ですが、長時間の集中を維持するのは難しいものです。集中力が落ちると読書効率も下がり、速読の効果が半減してしまいます。この問題に対処するためのいくつかの解決策を紹介します。
まず、「ポモドーロ・テクニック」のような時間管理法を取り入れることが効果的です。25分間集中して読書し、5分休憩するというサイクルを繰り返すことで、集中力を持続させることができます。また、自習室や図書館など勉強に適した環境の整備も重要です。スマホの通知をオフにし、静かで適度な明るさの場所を選びましょう。
さらに、読書前の短いマインドフルネス瞑想や深呼吸も集中力向上に役立ちます。脳に十分な酸素を送ることで、集中力と情報処理能力が高まります。これらの方法を組み合わせることで、より長い時間、高い集中状態を維持することができるでしょう。
読書素材別の適切なアプローチ方法
すべての文章に同じ速読テクニックを適用するのは効率的ではありません。読書素材の種類によって、最適なアプローチ方法は異なります。ここでは学生生活でよく読む素材ごとの効果的な読み方を紹介します。
教科書や参考書では、まず章の最初と最後、見出しや太字部分を読んで全体像を把握し、次に詳細を理解する方法が効率的です。文学作品では、ストーリーの流れを追うため、会話部分は速く、描写部分はイメージを作りながら読むといった使い分けが有効です。
学術論文では、要旨(アブストラクト)と結論を先に読み、図表を確認してから本文に進む方法が時間の節約になります。新聞や雑誌記事は、「逆ピラミッド構造」で書かれていることが多いため、最初の段落に注目すると概要をつかみやすくなります。
このように、読む素材に合わせて速読テクニックを使い分けることで、より効率的に必要な情報を得ることができます。テスト範囲や課題の目的意識を持ち、それに適した方法を選ぶことが速読マスターへの近道です。
速読トレーニングアプリ・ツールのまとめ
無料で使える速読トレーニングアプリ
速読を効率的に習得するため、さまざまな無料アプリやツールが開発されています。中でも学生におすすめなのは、一定の速度でテキストを表示する「RSVP(Rapid Serial Visual Presentation)」方式のアプリです。これは単語や文章のチャンクを一定のスピードで表示することで、集中して速く読む訓練ができます。
例えば「Spreeder」や「ReadMe!」などのウェブサイトやアプリでは、自分の読みたいテキストを入力し、表示速度を調整して練習することができます。また「Acceleread」のようなゲーム感覚で速読トレーニングができるアプリもあり、空き時間にスマホで気軽に取り組めるのが学生には魅力的です。
これらのアプリの多くは無料版と有料版があり、基本的な機能は無料で利用可能です。サイト上でのプライバシーポリシーを確認し、個人情報の取り扱いに注意したうえで活用しましょう。
効果的な速読補助ツール
アプリ以外にも、読書効率を高めるための様々なツールがあります。例えば、読書ガイド(定規のような形状で、読んでいる行だけを表示するもの)は、集中力の向上と不要な視線の動きを防ぐのに役立ちます。デジタルデバイスでの読書では、ブラウザ拡張機能として提供されている速読ツールも便利です。
また、音声読み上げ機能を活用する方法もあります。教科書や講義ノートをテキストに変換し、通常より速い速度で再生することで、速いペースでの情報処理に脳を慣れさせることができます。聴きながら目で追うことで、聴覚と視覚の両方を使った学習が可能になります。
さらに、マインドマップやノートテイキングアプリを併用することで、読んだ内容の整理と記憶の定着を促進することができます。読書と同時に重要なポイントを視覚的に整理することで、理解度と記憶力の向上が期待でき、テスト勉強の効率も上がります。
デジタルとアナログの併用法
速読の習得には、デジタルツールとアナログな方法の両方を適切に組み合わせることが効果的です。例えば、基本的なトレーニングはアプリで行い、実践は実際の教科書や参考書で行うという方法が考えられます。
デジタルツールのメリットは、進捗の記録や速度の調整が容易なことです。一方、紙の教科書や印刷した資料でのトレーニングは、目の疲れが少なく、ページめくりという物理的な動作が読書の感覚を強化するというメリットがあります。
おすすめの併用法としては、朝の通学時間はアプリで短時間集中して基礎トレーニングを行い、放課後は図書館で実際の教科書や資料を使って実践するという方法があります。また、スマホでオンラインニュースを速読し、週末には教科書で長文読解の練習をするといった使い分けも効果的です。
デジタルとアナログ、それぞれの良さを活かしながら、自分の学習スタイルに合った速読習慣を構築していきましょう。最終的には、どんな形式の文章でも効率よく読めるようになり、学習時間の短縮と成績向上につながるでしょう。
よくある質問(FAQ)
速読と理解度は両立できますか?
速読と理解度は確かに両立可能です。適切なトレーニングを受けた速読者は、通常の読者と同等かそれ以上の理解度を維持したまま、数倍の速さで読むことができます。
速読は単に目を速く動かすこと
ではなく、脳の情報処理能力を向上させる総合的なスキルです。実際、速読者は通常よりも高い集中状態で読むため、内容への没入度が増し、テスト勉強や課題読解での理解度が向上することもあります。
ただし、すべての文章を同じ速度で読むのは適切ではありません。難しい数式や重要な定義は必要に応じてペースを落とし、基本的な説明や既知の内容は速く読むなど、柔軟に速度を調整することが重要です。速読の真の目的は「状況に応じた最適な読書速度を選択できる能力」を身につけることだと言えます。
1日どれくらいの時間を速読トレーニングに費やすべきですか?
速読トレーニングの理想的な時間は、初心者の場合、1日15〜20分程度から始めるのが適切です。短時間でも毎日継続することが、長時間不定期に練習するよりも効果的です。学校の空き時間や通学時間を利用して、コンスタントに取り組むことをおすすめします。
慣れてきたら徐々に時間を延ばし、30分程度のトレーニングを週3〜5回行うのが効果的です。ただし、目の疲れを感じたら無理をせず休憩を取ることが大切です。速読は脳と目の両方を使うトレーニングなので、適度な休息も学習効果を高めるために重要です。
また、トレーニングと実践を分けて考えるのも有効です。専用のトレーニング時間とは別に、普段の教科書読解や課題文献を読む際に、学んだテクニックを意識的に適用してみましょう。実際の学習場面での応用が、スキルの定着には最も効果的です。
どんな種類の本でも速読は可能ですか?
基本的にはどんな種類の文章でも速読の技術を適用することは可能ですが、内容や目的によって最適な読み方は異なります。効率的な学習のためには、文章のタイプに応じた速読法の使い分けが重要です。
教科書や参考書は、内容の構造がしっかりしているため、速読に適しています。特に基礎的な説明部分は速く読み、重要な定義や公式などは丁寧に読むという使い分けが効果的です。文学作品は物語を楽しむために読むことが多いため、完全な速読は向かないこともありますが、描写部分と会話部分で速度を変えるなどの工夫ができます。
専門的な学術論文や数式が多い数学の教科書などは、完全な速読は難しいものの、まず全体を速読して構造を把握し、その後重要な部分を詳しく読むという段階的アプローチが有効です。速読は「すべての文章を同じように速く読む」ことではなく、「目的に応じて読書速度と方法を最適化する」ことだと理解しましょう。
速読のスキルは維持するために継続的な練習が必要ですか?
はい、速読スキルを維持するためには継続的な練習が必要です。他の多くのスキルと同じく、使わないと徐々に低下していく傾向があります。ただし、一度基本的な技術を身につければ、日常的な読書の中で意識するだけでもある程度維持できます。
継続のコツは、日々の学習に速読を取り入れることです。テスト勉強、課題読解、情報収集など、あらゆる読書場面で速読の技術を意識的に活用しましょう。また、定期的に自分の読書速度を測定し、記録することでモチベーションを維持することもできます。
速読スキルを維持・向上させるためには、週に1〜2回、10〜15分程度の集中的なトレーニングを続けることが理想的です。これは長期的な学習習慣として定着させれば、大学受験や就職活動、将来の仕事においても大きなアドバンテージとなるでしょう。
子どもにも速読トレーニングは有効ですか?
中高生以上の子どもにとって、基本的な速読トレーニングは非常に有効です。学年が上がるにつれて読む量が増えていく学校教育において、効率的な読書スキルは大きなメリットとなります。特に、受験勉強や定期テスト対策において、読書速度の向上は時間の節約と情報吸収量の増加につながります。
ただし、小学生など読解力がまだ発達途上の子どもには、まず基本的な読解力を養うことが優先です。速さよりも理解を重視し、文章を正確に読む習慣をつけることが大切です。中学生以上になれば、基本的な速読テクニック(指を使った読書、周辺視野の拡大など)を徐々に導入していくことができます。
高校生や大学受験生にとっては、速読は非常に実用的なスキルです。模試や過去問を解く際の時間管理、大量の参考書をこなす効率性など、様々な場面で役立ちます。学習塾や受験対策講座でも速読の講座を設けているところがあり、受講してみるのも良いでしょう。
速読マスターへの道:まとめと次のステップ
速読は単なるテクニックではなく、学習効率を大幅に向上させる重要なスキルです。本記事で紹介した基本ステップとテクニックを実践すれば、誰でも読書速度を2〜3倍に向上させることが可能です。
まず眼球運動の改善から始め、周辺視野の拡大、サブボーカリゼーションの抑制、集中力の向上へと段階的に取り組みましょう。フィンガーリーディングやチャンキングなどの具体的テクニックも効果的です。英語文献を読む機会が多い学生は、英語特有の速読コツも覚えておくと役立ちます。
速読の習得には時間がかかりますが、毎日の学習に少しずつ取り入れることで、徐々にスキルは向上していきます。アプリやツールを活用し、デジタルとアナログの両方の読書環境で練習することで、より効果的に習得できるでしょう。
速読は単に「速く読む」ことが目的ではなく、「必要な情報を効率よく得る」ための手段です。テスト勉強や課題をこなす時間を短縮し、より多くの学びを得るための武器として、ぜひ速読スキルを身につけてください。